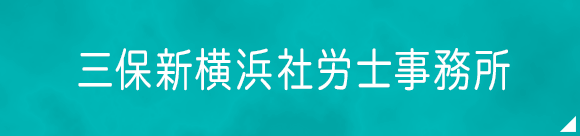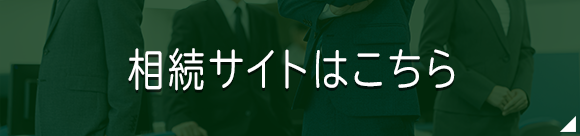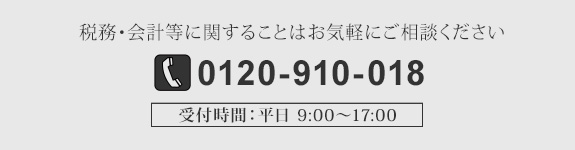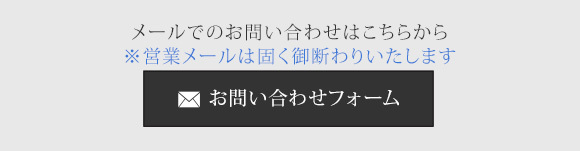トップページ > お知らせ/税の最新情報
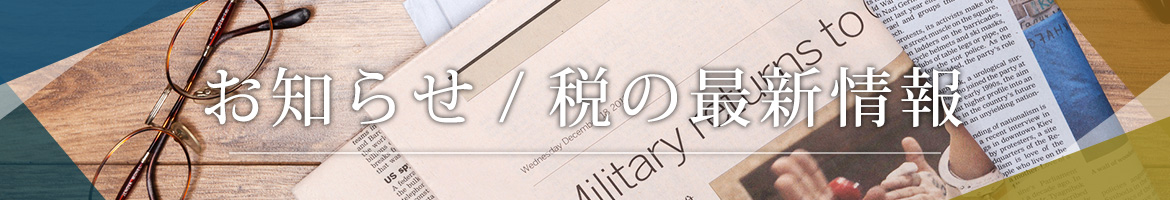
2026年
不動産の住所等変更登記が義務化されます
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
義務化される主な背景は、深刻化する「所有者不明土地問題」の解消です。
所有者不明土地とは、登記簿の情報が古いために、現在の所有者が誰なのか、どこに住んでいるのかすぐに分からない土地のことを指します。
スマート変更登記がご利用になれます
法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。
かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記がされ、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
詳しい制度のご案内や、手続きの詳細については、下記のリンクをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html
通勤手当の非課税限度額を確認しましょう
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、マイカー通勤者等に支給する通勤手当に係る所得税の非課税限度額が令和7年4月1日以後に支払われるべきものから引き上げられました。
年末調整で既に対応済みかとは思われますが、改めてご確認ください。
詳細は、こちらからご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
令和8年度税制改正大綱が閣議決定されました
閣議決定された「令和8年度税制改正大綱」の主なポイントは下記のとおりです。
【個人所得課税関係】
物価上昇局面における基礎控除等の対応
(1) 基礎控除
基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げる。
(2)給与所得控除
給与所得控除について、65万円の最低保障額を69万円に引き上げる。
住宅ローン控除の拡充と延長
・既存住宅のうち省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額の引上げ、子育て世帯への上乗せ措置の対象の拡充、床面積要件の緩和等
NISAの拡充
【資産税関係】
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(法人版事業承継税制(特例措置))延長
【法人課税関係】
特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
特定機械装置等について普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(即時償却)とその取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物については、4%)の税額控除との選択適用ができることとする。
ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は3年間の繰越しができることとする。
賃上げ促進税制の見直し
企業向け措置については、令和8年3月31日をもって廃止する。
中堅企業向け措置については、適用要件・税額控除率の見直しを行った上で、適用期限(令和9年3月31日)をもって廃止する。
研究開発税制の拡充等
【消費税関係】
インボイス制度導入に係る経過措置の見直し
いわゆる2割特例の終了後も、個人事業者については、これまで2割特例の対象となっている個人事業者も含め、納税額を売上税額の3割とすることができる措置を2年に限り講ずる(令和9年及び令和10年分)。
【その他】
ふるさと納税制度の見直し
特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割と次の金額とのいずれか低い金額(現行:個人住民税所得割額の2割)とする。
(見直し後の特例控除額の上限は193万円となる。)
防衛特別所得税(仮称)の創設
所得税額に対し、税率1%の新たな付加税として課す。
詳細については、「財務省ホームページ(税制)」をご参照ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html